生成AIの主な種類とは?
特徴や活用事例、選び方まで徹底解説
公開日:2025年07月07日
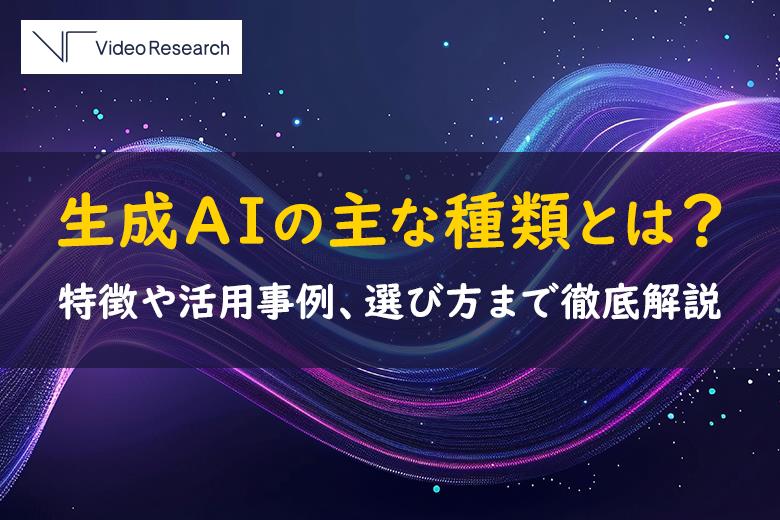
近年、生成AIは業務の生産性向上やアウトプットの標準化を支援する手段としてさまざまな領域で導入が進んでいますが、種類や用途、特徴について気になる方もいらっしゃるのではないでしょうか?
結論から申し上げると、生成AIは、用途別に「テキスト生成」「画像生成」「動画生成」「音声生成」「音楽生成」「プログラミングコード生成」の6種類に分類できます。
ビジネスでの導入やツール選定を検討するうえでは、種類ごとの特徴や違いを理解することが重要です。
本記事では、生成AIの主要な「6種類」に焦点を当て、それぞれの概要・代表ツール・活用事例・選定ポイントをわかりやすく解説します。
目次
- 1.生成AIの主な種類とは?用途別の6種類を紹介
- 2.生成AIの6種類の特徴
- 3.代表的な生成AIツール
- 4.生成AIの活用事例
- 5.生成AIの選び方
- 6.まとめ
1.生成AIの主な種類とは?用途別の6種類を紹介
生成AIは、生成するコンテンツの種類によって分類され、それぞれ得意な用途が異なります。
また生成AIは、文章や画像だけでなく、音声、動画、音楽、コードなど幅広いコンテンツを自動で生成できます。
以下は生成AIを種類別にまとめた表になります。
| 種類 | 生成内容 | 主な業務用途 |
|---|---|---|
| ①テキスト生成 | 文章・会話・要約 | メール文作成、議事録、チャット対応 |
| ②画像生成 | イラスト・写真・デザイン | 広告バナー、製品イメージ、資料挿絵 |
| ③動画生成 | 映像コンテンツ | マーケティング動画、商品紹介、SNS動画 |
| ④音声生成 | ナレーション・会話音声 | IVR※音声、研修教材、アナウンス |
| ⑤音楽生成 | BGM・楽曲 | 映像向けBGM、プロモーション楽曲 |
| ⑥コード生成 | プログラムコード | スクリプト自動生成、UIコード補完 |
| その他 | 3Dモデル、資料構成案、マルチモーダル生成 | AR/VR設計、スライドのたたき台、画像と説明文の同時生成など |
※電話自動応答システム
そもそも生成AIとは?
生成AIとは、テキスト、画像、音声、プログラムコードなど、さまざまなコンテンツをAIが自動で生成する技術です。これまで人の手によって行われていた創造的な作業を、一定の品質とスピードで代替・支援できる点において、企業活動における生産性向上や標準化の手段として注目されています。
生成AIについての詳細は、以下の記事をあわせてご確認ください。
2.生成AIの6種類の特徴
生成AIは、生成するコンテンツの種類に応じて用途や得意分野が異なります。ここでは主要な6種類について、それぞれの特徴とビジネスでの活用シーンを紹介します。
①テキスト生成AI
テキスト生成AIは、自然言語処理※を活用して、人間のような文章を自動で生成する技術です。チャットボットによる顧客対応や議事録作成、要約、翻訳、企画書の草案作成など幅広い業務で活用されています。近年では、対話の流れを理解しながら応答する能力も向上しており、ビジネスの文脈に適した表現を出力する精度も高まっています。
※人間の言葉(自然言語)をコンピューターが理解、解析、生成する技術
②画像生成AI
画像生成AIは、テキストで与えた指示からイラストや写真風の画像を自動生成します。
広告クリエイティブや資料の挿絵、製品デザインの試作など、ビジュアル作成業務の短縮と品質向上に寄与します。MidjourneyやStable Diffusionなどのツールは、芸術性やリアリティの表現に強みを持ち、専門的なデザインスキルがなくても高品質な画像が得られる点が評価されています。
③動画生成AI
動画生成AIは、画像やテキスト、音声を組み合わせて、動画コンテンツを自動で構成・生成します。
企業紹介や社内研修コンテンツ、SNS向けの短尺動画などに利用され、制作時間とコストの削減につながります。ツールによっては、ナレーションや自動字幕を追加できるツールも増えており、映像制作のハードルを下げています。
④音声生成AI
音声生成AIは、入力されたテキストから自然な音声を生成します。ナレーションや自動音声案内、eラーニング教材の音声作成などに活用されており、多言語・多声質への対応が進んでいます。感情表現が可能なツールも登場し、より人間らしい発話が求められるシーンでも利用価値が高まっています。
⑤音楽生成AI
音楽生成AIは、メロディやコード進行を自動で作曲し、BGMやジングルなどの音楽コンテンツを生成します。
著作権フリーで安心して使える音源を迅速に用意できるため、動画や広告、展示会などのBGM制作に幅広く使われています。
⑥コード生成AI
コード生成AIは、自然言語による指示から、HTMLやJavaScript、Python、SQLなどのプログラムコードを自動生成します。
Webアプリや業務システムの初期開発、定型処理の自動化、プロトタイプ作成などに有効で、開発効率の向上や属人化の防止にも貢献します。非エンジニアでも簡単なツール構築が可能になる場面が増えています。
その他の生成AI
近年では複数の生成機能を統合したマルチモーダル型AIも注目を集めています。
これはテキスト、画像、音声などを横断的に扱えるAIで、たとえば資料構成からスライド案まで一括での提案、画像を見ながら説明文の生成もできます。一つのツールで複数の成果物をまとめて生成できる点が大きな特徴であり、部門や業務の垣根を超えた活用が期待されています。
3.代表的な生成AIツール
生成AIを活用するうえで重要なのが、用途に応じたツールの選定です。特に、近年では、複数の種類に対応するマルチモーダル型のAIが主流となりつつあり、活用シーンはさらに拡大しています。
以下は、代表的な生成AIツールとそれぞれの特徴をまとめた表になります。
代表的な生成AIのベンダー/ツールと対応分野(2025年6月時点)
| ベンダー名 | ツール名 | テキスト生成 | 画像生成 | 動画生成 | 音声生成 | 音楽生成 | コード生成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI | ChatGPT + DALL·E + GPT-4o |
〇 | 〇 | △※1 | 〇 | × | 〇 |
| Gemini 2.0 | 〇 | 〇 | △※2 | 〇 | △※3 | 〇 | |
| Anthropic | Claude | 〇 | 〇※4 | × | × | × | 〇 |
| Stability AI | Stable Diffusion | △※5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| Midjourney | Midjourney | × | 〇 | × | × | × | × |
| Runway | Runway | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
- 「Sora」という高性能な動画生成モデルを発表済みですが、現在は限定提供のみとなっています。
- 「Veo」という動画生成モデルを発表済みですが、現在は限定提供にとどまっています。
- 「Lyria」という音楽生成モデルを開発しており、YouTube Shortsの機能「Dream Track」などで一部クリエイター向けに実験的に提供されていますが、単独のツールとしては提供されていません。
- Claude 3モデルファミリーは、画像入力(Vision)に対応しており、画像の内容を理解しテキストで応答することはできますが、テキストから画像を生成する機能はありません。
- 主力は画像生成ですが、「Stable Beluga」などの言語モデルも開発・提供しています。
各生成AIツールの商用利用可否(2025年6月時点)
内容は2025年6月時点の情報に基づいています。商用利用の可否や対応機能はベンダーの方針変更により変動する可能性があります。
最新の利用条件は、お手数ですが注釈に記載の公式ページをご確認ください。
| ベンダー名 | ツール名 | 商用利用 | 補足 |
|---|---|---|---|
| OpenAI | OpenAI ChatGPT + DALL·E + GPT-4o |
〇※1 | ChatGPTの有料プラン(Plus、 Team、 Enterprise)やAPI経由での利用は商用利用が可能です。DALL·E 3で生成した画像についても、利用規約の範囲内で商用利用が認められています。 |
| Gemini 2.0 | 〇※2 | Google CloudのVertex AIプラットフォームやGoogle Workspaceの有料プランを通じて提供されるGeminiモデルは、商用利用が可能です。 | |
| Anthropic | Claude | 〇※3 | API経由や、Amazon Bedrockなどのプラットフォームを通じた利用は商用契約に基づき、商用利用が可能です。 |
| Stability AI | Stable Diffusion | 〇※4 | Stable DiffusionはOpenRAIL++ライセンスで商用利用が可能です。ただし、使用モデルごとのライセンス確認が必要です。 |
| Midjourney | Midjourney | 〇※5 | 有料プラン(Standard、 Pro、 Mega)では、生成した画像の所有権が付与され、商用利用が可能です。無料プランでは商用利用できません。 |
| Runway | Runway | 〇※6 | 有料プランでは、生成した動画や画像のウォーターマーク(透かし)がなくなり、商用利用が可能になります。無料プランでは商用利用ができません。 |
- 参考:https://openai.com/ja-JP/policies/usage-policies/
- 参考:https://cloud.google.com/vertex-ai
- 参考:https://www-cdn.anthropic.com/6b68a6508f0210c5fe08f0199caa05c4ee6fb4dc/Anthropic-on-Bedrock-Commercial-Terms-of-Service_Dec_2023.pdf
- 参考:https://huggingface.co/spaces/CompVis/stable-diffusion-license
- 参考:https://docs.midjourney.com/hc/en-us/articles/32083055291277-Terms-of-Service
- 参考:https://runwayml.com/terms-of-use
4.生成AIの活用事例
生成AIは、単なるテクノロジーのトレンドにとどまらず、実際の業務プロセスを変革する実用的な手段として注目されています。特に、クリエイティブ業務やドキュメント作成、カスタマー対応など、属人化しやすい業務の標準化と効率化に寄与しています。以下は企業の代表的な5つの活用事例です。
- 事例1:議事録作成の自動化(テキスト生成)
- 事例2:営業資料・提案書のたたき台作成(テキスト+画像生成)
- 事例3:チャットボットによるカスタマー対応の強化(テキスト・音声生成)
- 事例4:製品紹介動画・BGMの自動生成(動画・音楽生成)
- 事例5:アプリ開発支援(コード生成AI)
それぞれ詳しくご紹介します。
事例1:議事録作成の自動化(テキスト生成)
会議や打ち合わせの音声をAIがリアルタイムで文字起こしし、要点の整理や要約を自動で実施します。発言内容の整理やアクションアイテムの抽出も可能であり、議事録作成の省力化と品質の均一化が期待できます。
導入効果の例
- 議事録作成時間の大幅短縮
- 担当者ごとの品質のばらつきを解消
- 情報共有のスピード向上
事例2:営業資料・提案書のたたき台作成(テキスト+画像生成)
構成案や導入文などをテキスト生成AIで作成し、さらに提案内容に適したビジュアルを画像生成AIで自動生成することで、資料の初稿作成を効率化できます。
導入効果の例
- 提案書初稿の作成時間を半減
- 経験の浅いメンバーでも一定レベルの資料が作成可能
- 見た目の統一性・品質の底上げ
事例3:チャットボットによるカスタマー対応の強化(テキスト・音声生成)
カスタマーサポート業務では、FAQや一次対応を生成AIベースのチャットボットが自動で対応します。さらに、音声生成AIと連携させることで、電話応対(IVR)も自動化され、問い合わせ対応の即時性と正確性が向上します。
導入効果の例
- 問い合わせ対応件数の半数以上を自動処理
- サポート担当者の負担軽減と離職リスクの低減
- 顧客満足度の向上
事例4:製品紹介動画・BGMの自動生成(動画・音楽生成)
商品説明動画や展示会用映像を自動生成する取り組みが進められています。テキストや画像素材をもとに構成された動画に、音楽生成AIで生成した著作権フリーのBGMを組み合わせれば、制作コストと時間を削減できます。
導入効果の例
- 動画制作コストや期間の削減
- 多様な領域を内製し、短納期対応が可能
- ターゲット別に複数パターン展開が容易であり、訴求力向上に寄与
事例5:アプリ開発支援(コード生成AI)
自然言語からHTMLやJavaScript、Pythonなどのコードを自動生成し、UI部品やAPI接続処理のたたき台作成に貢献します。
エンジニアの手作業を減らすことで開発スピードが向上し、テストコードの自動生成によって品質面でも一定の効果が期待されています。
導入効果の例
- コーディングやレビュー作業の負荷軽減
- テストコードや定型処理の自動化による品質向上
- 非エンジニア部門によるプロトタイプ作成も可能
5.生成AIの選び方
生成AIの導入を検討する際、話題性や知名度だけでツールを選ぶのではなく、自社の業務課題や活用目的に即したものを選定することが重要です。
どの業務を効率化したいのか、何を生成する必要があるのかを明確にしたうえで、目的に応じたツールの選定が成果に直結します。
以下は生成AIを選ぶ際に押さえておきたい5つの観点です。
それぞれご紹介します。
観点①:利用目的・業務との適合性
検討の際にもっとも重視すべきは「何を生成したいのか」です。生成AIには、テキスト、画像、音声、コードなど多様な種類があり、それぞれ得意分野が異なります。まずは「何を生成したいか」を明確にし、業務に合ったAIを選びましょう。
【観点例】
- 議事録や提案書の作成がしたい → テキスト生成AI(ChatGPT、Claude)
- マーケティング素材の作成がしたい → 画像生成AI(Midjourney、DALL·E)
- FAQ対応や音声案内がしたい → 音声生成AI(ElevenLabs、VOICEVOX)
観点②:操作性・社内展開のしやすさ
業務部門のメンバーの日常的利用を想定するなら、UIのわかりやすさやノーコード対応の有無が重要です。複雑な設定やスクリプトが不要なツールであれば、現場主導での活用が進みやすいです。 また、既存の業務ツール(Office製品、Slack、Notionなど)と連携できるどうかも確認しておきたいポイントです。
【観点例】
- ノーコードで利用できるか
- UIが直感的で習得しやすいか
- ExcelやSlack、Notionなどと連携できるか
観点③:商用利用・ライセンスの明確さ
生成されたコンテンツをホームページなどに使う場合、商用利用が可能か、著作権の扱いはどうなっているかを必ず確認するべきです。無料プランでは商用利用が制限されているケースや著作権がユーザーに帰属しないケースもあるため、利用想定に応じて有料プランの契約も視野に入れる必要があります。
【観点例】
- 商用利用が無料プランでも許可されているか
- 著作権がユーザーに帰属するか
- 公開資料や製品への使用が可能か
観点④:セキュリティ・データ保護
業務データをAIに入力する以上、情報漏えいや不正利用への対策も必要です。必ずツールの運用ポリシーを事前に確認しておきましょう。
【観点例】
- 入力データはAIの学習に使われないか
- 国内または指定リージョンで処理されるか
- ユーザーやプロジェクト単位での権限管理ができるか
観点⑤:費用対効果
ツール導入にかかるコストと、業務改善によって得られる効果を比較し、投資対効果の高いツールを選定する必要があります。無料トライアルやPoC(概念実証)が可能であれば、段階的にスケールさせる方法もよいでしょう。
【観点例】
- 従量課金か月額制か、料金体系を確認
- 無料トライアルやPoCで効果を見極められるか
- 小規模から始めて段階的に拡大できるか
6.まとめ
生成AIは、多様なコンテンツを自動生成し、業務の効率化や標準化に貢献する技術です。
近年では用途別に特化したツールが登場し、導入事例も広がっています。
本記事では、代表的な6種類の生成AIの特徴や活用事例、ツール選定のポイントを紹介しました。導入にあたっては、目的や業務との適合性、操作性、ライセンス、セキュリティ、費用対効果などを踏まえ、自社に合ったツールを見極めることが重要です。
当社では顧客の業務課題と向き合い、高度な実効性のあるソリューションを提供するため、「生成AI技術の研究開発」を実施しています。
また、これまでのシステム開発・運用経験、また業務フローの可視化と課題抽出などで本質的な改善点を導き出し、生成AIを含めたソリューションの導入支援を行うBPRコンサルティングも提供しています。
ご興味をお持ちいただけましたら、お気軽に以下よりお問い合わせください。


