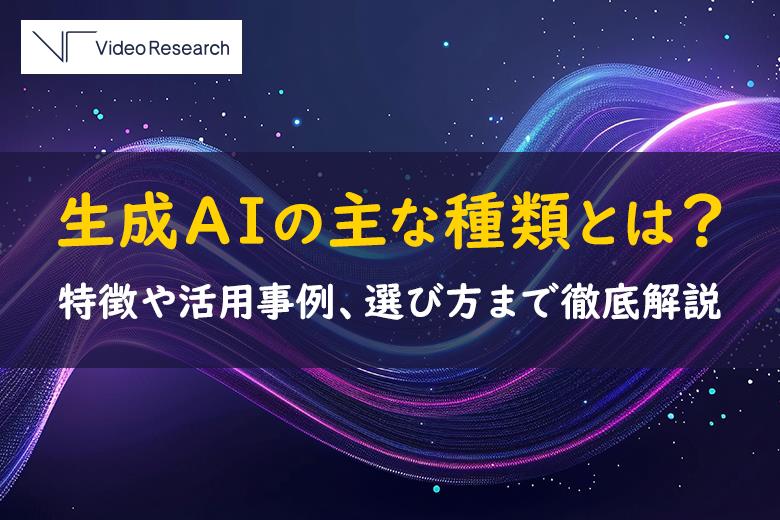生成AIとは?
種類や代表的なサービス、導入までのステップを
ロードマップで解説
公開日:2025年08月06日

「生成AIって最近よく聞くけど、実際にはどんなものなのか分からない」
「ビジネスの現場で導入が進んでいると聞くけど、本当に役立つの?」
このような疑問を持つ方も多いでしょう。
生成AIとは、テキストや画像、音声、動画といった多様なコンテンツを新たに自動生成するAI(人工知能)の総称です。一例として、ChatGPTやGeminiが挙げられます。
生成AIは、業務効率化やクリエイティブな作業の支援など、さまざまなシーンで急速に活用が進んでいます。しかし、ハルシネーション(事実と異なる情報の生成)や著作権問題など、利用にあたってはリスクも存在します。
本記事では、「生成AIとは何か」「どのような種類やツールがあるのか」「自分の業務にどう活用できるのか」などを解説しています。生成AIの導入を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
目次
1.生成AIとは
生成AIとは、テキスト、画像、音声、動画といった多様なコンテンツを新たに生み出すAI(人工知能)の総称です。
従来のAIは、既存のデータから予測や分類を行うのが主な役割でした。一方、生成AIは、学習したデータをもとに、新しい情報や表現を創造する能力を持っています。そのため、クリエイティブ分野からビジネス活用まで幅広い可能性を持つ技術といえるでしょう。
たとえば、ChatGPTを代表とするテキスト生成AIは、人間が書いたような自然な文章を生成し、レポート作成や問い合わせ対応を効率化できます。
生成AIに用いられている主な技術
生成AIは、深層学習(ディープラーニング)※1を中心とする複数の高度な先進的技術が利用されています。
代表的な用途ごとの技術とその概要は、以下の通りです。
| 用途 | 主な技術 | 概要 |
|---|---|---|
| テキスト生成 |
|
|
| 画像生成 |
|
技術ごとに異なる手法で画像を生成
|
- 深層学習(ディープラーニング):人間の脳の仕組みを模した「人工ニューラルネットワーク」を多層構造にして、データから複雑なパターンを学習する技術。
- 自然言語処理(NLP):人間の言語をコンピューターで理解・生成・翻訳などを行う技術。
- 敵対的生成ネットワーク(GAN):二つのAI(生成者と識別者)が競い合うことで、よりリアルな画像を生成する技術。
- 変分オートエンコーダー(VAE):データの特徴を抽出して、新たなデータを生成する技術。自然な画像生成に強みがある。
- 拡散モデル:画像を一度ノイズでぼかしてから、徐々にノイズを取り除いて鮮明な画像を生成する技術。自然かつ高精細な画像の生成に優れている。
従来のAIとの違い
従来の識別型AI(Discriminative AI)は、既存のデータの中から最適な答えを「選ぶ」ものであり、判断や分類、予測などが主なタスクでした。
一方、生成AIは、「0から1を生み出す」創造的なAIです。ジェネレーティブAI(Generative AI)とも呼ばれます。データから学習した知識をもとに、新たなアウトプットを「作る」ことが可能です。
代表的な用途ごとの技術とその概要は、以下の通りです。
| 項目 | 従来のAI(識別型) | 生成AI(生成型) |
|---|---|---|
| 主な役割 | 判定・分類・予測 | 新しいコンテンツの生成 |
| 例 | 画像認識、スパム判定 | テキスト・画像・動画の自動生成 |
| 技術 | 機械学習、ディープラーニング | ディープラーニング、生成モデル |
| 出力 | ラベルや確率などの識別結果 | 新たな文章・画像・音声など |
2.生成AIの種類と代表的なサービス
「生成AI」が生成できるコンテンツの種類は多岐にわたり、用途が異なるさまざまなサービスが登場しています。生成AIの種類と代表的なサービスを表形式で整理しました。
| 種類 | 特徴 | 代表的なサービス |
|---|---|---|
| テキスト生成AI | 人間のような自然な文章を生成。要約、翻訳、会話、資料作成など幅広く対応。 | ChatGPT(OpenAI)※6 Claude(Anthropic)※6 Gemini(Google)※6 |
| 画像生成AI | テキストから写真・イラスト・デザインなどのビジュアルを自動生成。 | Midjourney Stable Diffusion DALL·E(OpenAI) |
| 動画生成AI | 画像・音声・テキストなどを統合して動画を自動作成。 | Runway※6 Synthesia※6 |
| 音声生成AI | 入力したテキストから自然な音声を合成。感情や声質の選択も可能。 | ElevenLabs※6 VOICEVOX |
| 音楽生成AI | メロディやBGM、ジングルなどの楽曲を自動作成。著作権の心配が少ない。 | Soundraw |
| コード生成AI | 自然言語からプログラムコードを自動生成。 非エンジニアの補助にも有効。 |
GitHub Copilot Amazon CodeWhisperer |
※6 マルチモーダル型AI対応サービス:テキストだけでなく画像や音声など複数モーダルに対応する。
生成AIの種類についての詳細は、以下の記事をあわせてご確認ください。
3.生成AIの仕組み
生成AIは、大量のデータから、新しいコンテンツを自動で作り出す仕組みです。ユーザーからの指示(プロンプト)をもとに、次に来る単語や文を高精度で予測し、単語を一つずつつなげていくことで自然な文章を生成します。
言葉の出現パターンや文脈のつながりを理解し、入力文に対して「人間ならどう続けるか」を予測するため、長文でも一貫性を保ちながら論理的に文章を構成できる能力があります。
生成AIの仕組みについての詳細は、以下の記事をあわせてご確認ください。
4. 業務における生成AIの活用例
本章では、どのような業務の効率化に生成AIが活用できるのかについて解説します。業務部門別に業務プロセスと改善例をまとめました。
総務・管理部門
| 業務 | 改善例 |
|---|---|
| 紙資料や過去の契約書、社内規程の電子化・データベース化 | OCR※7と生成AIを組み合わせて紙資料を電子化し、横断検索や自動要約を実現。必要な情報の検索時間を大幅に短縮。 |
| 社内問い合わせ対応 | AIチャットボット導入で、社内問い合わせの自動化・即時回答を実現し、サポート部門の負担を軽減。 |
※7 OCR(光学文字認識):画像内の文字を読み取り、デジタルテキストに変換する技術。
営業・マーケティング部門
| 業務 | 改善例 |
|---|---|
| 広告・販促資料の作成 | 画像生成AIで広告バナーやSNS用画像を自動生成し、制作工数とコストを削減。 |
| 顧客データ分析、キャンペーン施策立案 | 顧客データや過去の広告効果データをもとに、AIが最適なクリエイティブやメッセージ案を提案。効果の高い広告素材を自動選定。 |
コールセンター・カスタマーサポート部門
| 業務 | 改善例 |
|---|---|
| 顧客問い合わせ対応 | AIチャットボットによる自動応答で、顧客への即時対応と応答率向上を実現。オペレーターの負担を軽減。 |
| FAQやナレッジベースの更新 | 過去の問い合わせデータをAIが分析し、よくある質問や課題を自動抽出。FAQの自動生成・更新に活用。 |
企画・広報部門
| 業務 | 改善例 |
|---|---|
| 広報資料や動画台本の作成 | 生成AIによるドキュメント自動生成・要約で、資料作成の時間を大幅に短縮し、職員の負担を軽減。複数案の自動生成により、成果物の質を向上。 |
| 社内外向けの発表資料作成 | 動画生成AIを活用し、プロモーション動画やeラーニング教材を低コスト・短期間で制作。 |
教育・人材開発部門
| 業務 | 改善例 |
|---|---|
| 研修教材やマニュアルの作成 | 社内ナレッジや過去の研修データを活用し、利用者に合わせた教育コンテンツを自動作成。 |
| アンケート分析、レポート作成 | 生成AIによる教材やマニュアルの自動生成、アンケート結果の自動分析・要約で、担当者の作業負荷を軽減。 |
5.生成AI導入までのロードマップ
続いて、生成AI導入までのロードマップをご紹介します。生成AIの導入ステップの例は、以下の通りです。
| STEP01 課題整理・目的設定 |
生成AI導入の目的と対象業務を明確化。社内ニーズと期待効果を整理。 |
|---|---|
| STEP02 ツール選定 |
用途適合性・セキュリティレベル・導入支援体制・ライセンス形態といった観点で比較する。 |
| STEP03 PoC(概念実証)実施 |
限定部署・業務範囲で試験導入し、実効性・精度・リスクを検証。 |
| STEP04 効果検証・評価 |
PoCの結果を定量・定性的に評価。業務改善効果やリスク低減の有無を確認。 |
| STEP05 運用設計・ルール整備 |
利用ガイドライン、セキュリティ対策、教育・研修体制の構築。 |
| STEP06 本格導入・展開 |
成果とノウハウをもとに全社展開。効果のモニタリングと継続改善体制を確立。 |
特に、STEP2のツール選定は、導入の成否を大きく左右する重要なステップです。目的と現場ニーズに合致したツールを選ぶことで、その後の検証や展開フェーズが格段にスムーズになります。
6.生成AI導入時に押さえるべき注意点とリスク4選
生成AIは高機能である一方、注意すべきリスクも存在します。過去データをもとに出力を行う性質上、学習内容に依存して不正確な結果や倫理的に不適切なコンテンツを生成する可能性があるためです。
具体的には、以下のリスクに注意が必要です。
| リスク | 概要・対策 |
|---|---|
| 著作権・知的財産権の侵害 | 生成AIが既存の著作物や商標、肖像権などを侵害するリスクがある。出力物の確認や利用ガイドラインの策定が必須。 |
| 情報漏えい | 機密情報や個人情報をAIに入力することで、外部流出のリスクが高まる。入力データの管理、アクセス権限の設定、セキュリティ対策の徹底が必要。 |
| ハルシネーション | 学習内容によって、事実と異なる内容や根拠不明な情報を出力する場合がある。人による内容チェックと検証を行う体制が求められる。 |
| その他 | 倫理的問題、プロンプトインジェクション(悪意ある指示による不正出力)、学習データの偏りによるバイアスなどにも注意が必要。適切なフィルタリングや利用ガイドラインの制定、モニタリングの仕組みの構築が求められる。 |
生成AIの安全な活用には、運用ルールの整備、情報の目視チェック、権利確認、ログ管理といった多層的な対策を講じることが不可欠です。
7.今後のトレンドと発展の可能性
生成AIの今後について、以下のようなトレンドが考えられます。
マルチモーダルAI
マルチモーダルAIは、テキスト・画像・音声を統合的に解析・生成する技術です。カスタマー対応や医療支援、エンタメなどで応用が進んでいます。
ガートナージャパン株式会社の調査※7によると、2027年には生成AIソリューションの40%がマルチモーダル化すると予測されています。
※7 Gartner、「生成AIのハイプ・サイクル:2024年」を発表 - 2027年までに生成AIソリューションの40%がマルチモーダルになると予測
RAG
RAGは、生成AIに既存の知識・ナレッジを検索・参照させたうえで、文脈を踏まえた自然な回答を生成する技術です。学習時点では含まれていない最新情報や社内固有の知識の反映を可能にします。この技術により、生成AIが出力した成果物の信頼性や検索精度の向上、業務効率化が期待できるでしょう。
社内ナレッジとの連携
問い合わせ対応や定型業務手順といった社内ナレッジと生成AIを連携させることで、社内QAや業務フロー支援が可能となり、ベテランの知見の形式知化や全社的な知識共有が進んでいます。
8.まとめ
生成AIは、「0から1を生み出す」技術であり、文章や画像、動画、音声といった多様なコンテンツを生成する力を持っています。文章・画像生成AI、動画生成ツールなど、すでに多くのサービスがビジネス現場で活用されており、業務の効率化・高度化に大きく貢献しています。
一方で、誤情報や著作権などのリスクもあるため、正しい知識とルールのもとでの運用が不可欠です。本記事で紹介した活用例や注意点、導入ステップを参考に、自社に適した生成AIの導入をぜひご検討ください。
当社では顧客の業務課題と向き合い、高度な実効性のあるソリューションを提供するため、「生成AI技術の研究開発」を実施しています。
また、これまでのシステム開発・運用経験、また業務フローの可視化と課題抽出などで本質的な改善点を導き出し、生成AIを含めたソリューションの導入支援を行うBPRコンサルティングも提供しています。
ご興味をお持ちいただけましたら、お気軽に以下よりお問い合わせください。