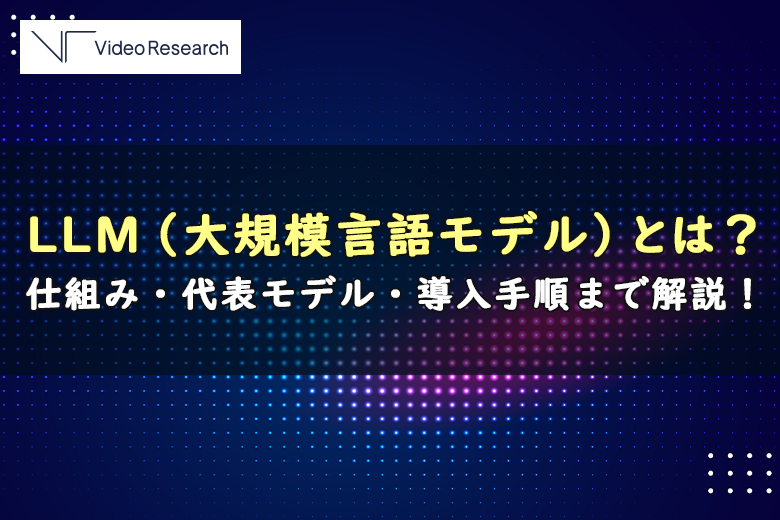LLMの仕組みをやさしく解説
できること・できないこと・事例も紹介
公開日:2025年09月29日

生成AIが急速に普及する中、「LLMの仕組み」を正しく理解したいと感じている方は多いでしょう。「生成AIは便利そうだけれど、どう動いているのか分からない」という声も少なくありません。
LLMは、人間のように自然な文章を理解・生成できるAIモデルのことを指します。
また、LLMの仕組みを端的に説明すると、①トークン化、②エンコード、③モデル処理、④デコードの4つのステップを経て自然な文章を生成します。
ただし、LLMから出力された文章は、あくまで統計的な「予測」に基づいて生成されたもので、必ずしも事実が保証されるわけではありません。LLMができることと限界を正しく理解し、適切に活用することが重要です。
本記事では、LLMの基本的な仕組みから、実務に役立つ具体的なユースケースまでわかりやすく解説します。
目次
1.LLMの仕組み
LLMの仕組みについて解説する前に、LLMとは何かについて解説します。
LLMとは
LLMは、膨大なテキストデータと深層学習により人間の言語を理解・生成する技術です。特にテキストに特化しており、文脈を踏まえた自然な会話を得意としています。
従来型のAIモデルよりも応用範囲が広く高精度で、質問応答・要約・翻訳など、私たちが日常で使う「自然な言語処理」に対応します。
また、他のシステムと連携しやすく、非エンジニアでも扱える手軽さが強みです。
LLMについての詳細は、以下の記事をあわせてご確認ください。
LLMの仕組み
LLMは、文章の意味や文脈を理解しながら、次に続く言葉を予測して文章を組み立てます。この仕組みを支える中核的な技術が、Transformerです。Transformerは、文章内の単語同士の関係性(文脈)を効率的に捉え、人間にとって自然に感じられる文章を素早く、的確に作る仕組みです。
LLMの動作は、大きく次の4ステップに分けられます。
- トークン化(Tokenization)
入力テキストを細かい単位「トークン」に分割する。 - エンコード(Encoding)
各トークンを数値ベクトルに変えて意味を表す。 - モデル処理(Transformerによる計算)
文脈を理解して次に来る単語の可能性を計算する。 - デコード(Decoding)
計算結果から単語を選び、順に文章を作る。
各ステップの詳細を解説します。
①トークン化(テキストを扱える形にする)
LLMは、人間が扱うそのままの文章を処理できません。そのため、まず「単語」や「サブワード」(単語の一部)に分割し、「トークン」と呼ばれる最小単位にすることが必要です。
例えば、「生成AIは便利です」 という文字列は、 「生成」「AI」「は」「便利」「です」の5トークンに分割できます。文章の区切り方はLLMの種類によって異なり、その粒度は生成の品質やトークン数にも影響します。
また、LLMが一度に処理できるトークン数(文章の長さ)の上限も考慮しましょう。上限を超える文章は一度に入力できないため、分割して入力する必要があります。
②エンコード(埋め込み)
次に、トークンを「ベクトル(数値の並び)」に変換して、単語の意味や関係性を数値的に表現します。
トークンを数値化する際には、似た意味を持つ単語はベクトル空間上で近い位置に配置されるという特徴があります。簡単にいうと、単語の関係を地図上に配置するようなイメージです。意味が近い単語は地図上の近い位置、意味が遠い単語は遠い位置に配置されると考えると分かりやすいでしょう。
例えば、動物の種類である「犬」と「猫」はベクトル空間上の位置が近く、これに比べて「犬」と「飛行機」は位置が遠くなります。
さらに、文章内での順序や位置情報も加えることで、LLMは「誰が」「何をした」などの文脈理解ができます。
なお、各トークンを数値化し、位置情報を付与したものを「入力ベクトル列」と呼びます。
③モデル処理(Transformer)
このステップでは、「エンコード」のステップで得られた「入力ベクトル列」がTransformerに入力され、より文脈を反映した新しいベクトル列へと変換します。
ちなみにTransformerとは、文章を理解したり、文章を作成したりするための「頭脳」のようなものです。人間が会話の流れや文脈を考えるように、Transformerも「どの言葉が大事か」「どの言葉と関係があるか」を考えながら処理します。
また、Transformerの特徴的な仕組みに、「Attention(注意)」機能があり、文章の中で「今どの単語に注目すべきか」を自動で判断します。例えば、「それは」という単語があった場合、その指示語が具体的にどの単語を指しているのかを見つけることが可能です。
長文を処理するには多くの時間が必要であるため、要約や分割、必要な部分の抜粋をして処理の効率化を図ります。
ちなみに 2017年ごろまでは、「CNN (畳み込みニューラルネットワーク)」や「RNN(回帰型ニューラルネットワーク)」といったモデルがLLMで使われていましたが、RNNのように文脈を理解できて、CNNのように並列処理ができる、つまりいいとこ取りのTransformerが主流になっています。
④デコーディング(文章生成)
デコーディングは、「モデル処理」で得られた「文脈を反映したベクトル」をもとに、Transformerは「次に続く単語」を予測するステップです。
ここでは、過去の膨大な学習で得られた知識パラメータとAttention機能を使って「次に続く単語の確率分布」を計算し、文章を生成します。
代表的な生成方法は以下の通りです。
- ● 貪欲法(Greedy Search):常に最も確率の高い単語を選ぶ生成方法。一貫性のある文章を作るが創造性は低い。
- ● ビームサーチ(Beam Search):複数の候補を同時に探索し、より良い単語の組み合わせを見つける。精度は高いが、計算コストは高い。
- ● Top-k/Top-pサンプリング:候補単語の範囲を限定し、多様性と品質のバランスを取る。
生成した単語を使い続けることで、長文でも文脈を保ち自然な文章を作成できるようになります。ただし、終了トークンや文字数の上限に達すると、テキスト生成は停止します。
2.LLMの仕組みから見るできることとできないこと
これまで解説したLLMの仕組みから、できること・できないことを表形式で整理しました。
| 分類 | できること(得意分野) | できないこと(不得意分野) |
|---|---|---|
| 文章処理 |
|
|
| コード生成 |
|
|
| アイデア創出 |
|
|
3.LLMの仕組みに起因する課題とその対策
前章で紹介した「LLMの不得意分野」は、LLM導入における課題ともいえます。代表的な課題と対策を表に整理します
| 課題 | 概要 | 対策 |
|---|---|---|
| 文脈や目的に合った「意図」の理解 | LLMは文脈を推測するが、人間の目的や背景までは理解できないため誤回答のリスクがある。 | 出力した文章をそのまま使うのではなく、人間が確認・判断を行うプロセスを組み込む。 |
| 長文を最後まで矛盾なく処理する | 入力できる情報量には上限があり、非常に長い文書では抜け漏れや矛盾が生じやすい。 | 要約や分割による前処理、重要箇所のみを抽出して入力する。 |
|
コードの動作検証や情報の真偽を自動で保証することはできない。 | 実行環境でのテストや、検索システムと組み合わせて根拠を提示する「RAG(検索拡張生成)」が有効。 |
|
LLMは既存データに基づく出力のため、独自の発想や倫理的判断はできない。 | アイデアのたたき台として活用し、最終的な企画立案や判断は人間が担う。 |
課題を理解した上で、人間の判断や追加ツールを組み合わせることで、LLMの安全かつ効果的な導入を実現できます。
4. まとめ
LLMは、膨大なデータと高度な技術により、自然言語処理を飛躍的に進化させました。また、技術進化に伴い、今後も多様な業務への応用が期待される技術です。
しかし、「予測ベース」という仕組みゆえに、LLMの利用には、誤情報の生成やセキュリティリスクも伴います。基礎知識と運用上の注意点を押さえたうえで導入を進めることが成功のポイントです。
当社では、顧客の業務課題と向き合い、高度な実効性のあるソリューションを提供するため、「生成AI技術の研究開発」を実施しています。
また、これまでのシステム開発・運用経験、業務フローの可視化と課題抽出などで本質的な改善点を導き出し、生成AIを含めたソリューションの導入支援を行うBPRコンサルティングも提供しています。
ご興味をお持ちいただけましたら、お気軽に以下よりお問い合わせください。