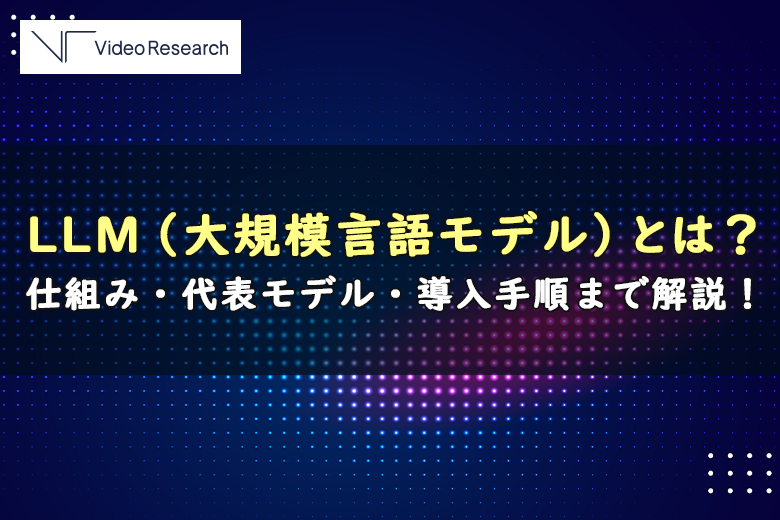生成AIとLLMの違いを解説!
業務導入で失敗しないための3つの視点を解説
公開日:2025年08月06日

生成AIが世間に普及するにつれて、ビジネスの現場でも導入が進んでいます。
しかし現場では、
「そもそもLLM(大規模言語モデル)と何が違うのか?」
「業務に取り入れてみたいが、どこから理解すればよいのか分からない」
といった悩みを抱えている方も少なくありません。
生成AIはLLMを基盤技術の一つとして活用しており、LLMが中心となってさまざまな生成AIサービスが成り立っています。ただし、生成AIすべてがLLMで動いているわけではなく、画像や音声などの生成には別の技術が使われている点も理解しておく必要があります。
本記事では、LLMと生成AIの違いや関係性をわかりやすく整理し、業務で使うときに押さえたい視点を解説します。
目次
1.LLMと生成AIの違い
LLM(大規模言語モデル)とは、自然言語処理(NLP)の分野で発展してきたAIモデルの一種です。大量のテキストデータを学習し、文脈に沿った自然な文章を生成できる点が特徴で、ChatGPTをはじめとする、チャット型AIの基盤として広く使われています。
一方、生成AIは、テキスト・画像・音声・コードなどのコンテンツを自動生成するAIの機能やサービス全体を指します。
LLMは、生成AIの構成要素の一つであり、とくにテキスト生成を担う技術的中核に位置づけられます。
表で両者の違いを整理すると以下の通りです。
| 項目 | LLM(大規模言語モデル) | 生成AI |
|---|---|---|
| 定義 | 言語を理解・生成するためのAIモデル(技術) | テキスト・画像・音声などを自動生成するAIの総称(機能) |
| 役割 | 主にテキスト生成を担う | 複数の技術を組み合わせて、多様なコンテンツを自動生成する |
| 使用される領域 | テキスト作成、要約、チャット、コード生成など | テキスト生成、画像生成、音声合成、動画生成など |
| 代表的な技術/サービス | OpenAIのGPTシリーズ、GoogleのGemini、AnthropicのClaude など | ChatGPT、Midjourney、Stable Diffusion、Voicemod など |
LLMについての詳細は、以下の記事をあわせてご確認ください。
生成AIとは
生成AIとは、テキスト・画像・音声・コードなどのコンテンツを自動生成するAIの総称です。テキスト生成では主にLLMが使われ、画像生成にはDiffusion Modelが使われるというように、用途に応じたさまざまなAI技術を活用しています。
生成AIについての詳細は、以下の記事をあわせてご確認ください。
両者の関係性
生成AIは複数の技術で構成されています。その中で、テキスト生成を担う技術の代表がLLMです。
業務で生成AIを使いこなすには、LLMの仕組みや制限も理解しておくことが前提条件となります。特に、文章を生成する場合、どのLLMを採用するかが成果を大きく左右するため、選定が非常に重要です。
LLMが動作する仕組みは、以下のように整理できます。
LLMの仕組み
- 大量のテキストを学習して単語や文のパターンを把握
- 単語の関係性をベクトル(数値)で表現
- 入力文に対して、もっとも自然な次の単語を予測して文章を生成
このような仕組みにより、LLMは自然で文脈に沿った文章を生成できます。
2.LLMを使う生成AIとその他の生成AI
すべての生成AIが、LLMを用いて動いていると誤解されることがありますが、実際には用途に応じてさまざまな技術が使われています。
LLMを使う生成AIツールの代表例
LLMの代表的な用途として、文書作成、要約、翻訳、チャット対応、コード生成などがあります。上記のような高度な文脈理解と自然な言語生成が求められる場面で、LLMが有効に機能します。
代表例
- ChatGPT:OpenAI の最新 GPT 系モデル(例:GPT 4o、GPT 4.1 など)や Reasoning 系モデル(o3 など)を利用できるチャット AI サービス。会話型の自然な応答が強み。
- Claude:高精度の応答とセキュリティに配慮した設計で、業務利用が拡大中。
- Gemini:Googleが開発したLLMで、検索や業務支援機能を備えた多機能な生成AIサービス。
LLM ではなく専門アルゴリズムで生成を行う代表的な画像・音声ツール
画像や音声などテキスト以外の生成には、LLMではなく別のアルゴリズムや専用の生成モデルが用いられます。視覚・聴覚的な出力を得意とするモデルは、動画制作、広告、プレゼン資料の素材生成などに活用されます。
ただし、テキスト入力の理解にはCLIPなどのTransformer系の言語エンコーダや、GPT-4のようなLLMが補助的に使われるケースもあります。
代表例
- Midjourney/Stable Diffusion:芸術的な画像生成が可能なAI。広告素材やデザイン制作の領域で活用される。
- DALL·E:テキストから画像を生成するAI。ベース技術はDiffusion Model。
- Voicemod/Voice AI:音声の生成・変換に特化。ナレーションやバーチャルキャラクター用途で利用される。
目的や利用シーンに応じた技術選定が重要
生成AIは、目的によって使うべき技術が異なります。テキスト生成ならLLM、画像ならDiffusion、音声なら音響系モデルというように、各技術には得意領域があるためです。
たとえばLLMは、議事録作成、FAQ自動化、マニュアル要約、コードの自動生成など、言語処理を伴う業務に適しています。
3.生成AIとLLMを業務で使うときに押さえたい3つの視点
生成AIやLLMを業務に導入する際には、業務に適したモデル選定や環境整備が重要です。ここでは、業務活用時に押さえておきたい3つの視点を解説します。
①出力品質と日本語の精度を確認する
生成AIの出力品質は、搭載されているLLMの性能に大きく依存します。
GPT-4.5やClaude 4などの最新モデルは、文脈理解力が高く、自然な文章生成や意図の正確な解釈に長けています。しかし、モデルによっては、日本語の表現に違和感が見られるケースもあるでしょう。
日本語を多く扱う業務では、日本語対応に優れたtsuzumi(NTT)、Llama-3-ELYZA-JP(ELYZA)などの日本語特化のLLM選ぶことが重要です。導入前には、自社のFAQや議事録テンプレートなどを用い、出力内容の自然さ・正確さ・一貫性を検証しましょう。
②導入形態とセキュリティ要件を確認する
生成AIは、「クラウド型」と「オンプレミス型」の二つの形態があります。
クラウド型は初期導入が容易で、すぐに使い始められる利点があります。一方で、入力データが外部に送信されるため、機密性の高い情報を扱う業務ではリスクが伴います。
オンプレミス型は、自社のセキュリティポリシーに基づいた制御が可能で、個人情報や営業機密を扱う企業では有効な選択肢です。
また、API連携の有無もポイントです。他システムと連携できるかどうかで、業務プロセス全体の効率化に差が生まれます。導入前には、自社の情報管理ルールやシステム要件との整合性をしっかり確認しましょう。
③社内データとの連携設計を行う
生成AIを業務にフィットさせるには、社内情報との連携が欠かせません。たとえば、製品情報や社内マニュアル、業務フローをAIに組み込むことで、業務に即した回答を得られます。
社内情報との連携には、主に「RAG(Retrieval-Augmented Generation)」が用いられます。RAGは、あらかじめ指定したデータベースや社内文書から関連情報を検索し、それをもとにLLMが回答を生成する仕組みです。FAQ応答や社内ポータル、業務サポートツールなどでの活用が進んでいます。
また、プロンプト(指示文)の設計やモデルの特性理解も重要です。たとえば、「〇〇について5つのポイントで簡潔に教えて」といった構造化された指示文は、より安定した出力につながります。一方で、あいまいな表現や前提条件が不足した質問では、モデルが情報を補完しようとして事実と異なる内容(ハルシネーション)を生成しやすくなります。
業務活用においては、単にモデルに任せるのではなく、「どこまでをAIが担い、どこから人が補完するか」という設計視点と、実運用に即したプロンプトのチューニングが不可欠です。
4. まとめ
生成AIとLLMの違いは、「範囲」と「技術構成」にあります。LLMはあくまで自然言語処理に特化したAIモデルであり、生成AIはテキストだけでなく画像・音声・コードなどを含む幅広い生成技術・サービスの総称です。
生成AIを業務利用する際には、目的に応じた技術選定が不可欠です。また、「出力品質」「セキュリティ要件」「社内データとの連携」といった視点を押さえることで、生成AIで利用する技術モデルの選定や運用環境の整備において、的確な判断を下すための軸を得られるでしょう。
当社では、顧客の業務課題と向き合い、高度な実効性のあるソリューションを提供するため、「生成AI技術の研究開発」を実施しています。
また、これまでのシステム開発・運用経験、また業務フローの可視化と課題抽出などで本質的な改善点を導き出し、生成AIを含めたソリューションの導入支援を行うBPRコンサルティングも提供しています。
ご興味をお持ちいただけましたら、お気軽に以下よりお問い合わせください。