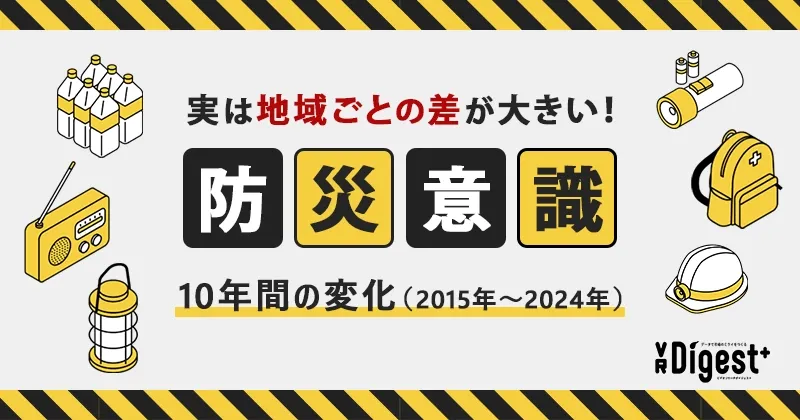実は地域ごとの差が大きい!防災意識10年間の変化(2015年~2024年)
- この記事はこんな方にオススメ!
-
- 防災に興味がある方
- 災害時の情報収集に関心がある方
- 生活者の変化に興味のある方
9月1日は防災の日です。日本は災害大国と言われるほど災害の多い国。最近では、2024年に発生した能登半島地震が記憶に新しく、現在も復興の途上にあります。さらに、今後は南海トラフ地震や首都直下地震といった甚大な被害が予想される地震の発生も懸念されています。また、地震に限らず、水害や風害などの気象災害も近年頻発しており、防災は日本に暮らす人々にとってますます重要な課題となっています。
では実際に人々の防災意識は高まってきているのでしょうか。
今回は、50年以上にわたり日本の生活者の意識動向を調査し続けているビデオリサーチ「ACR/ex」より、生活者の防災に関する意識変化を調査結果としてまとめてみました。
約30%が防災グッズを所有、地区によって所有率10pt以上の差
2024年時点で、10年前(2015年)と比べると防災グッズの所有率はどのように変化しているのでしょうか。
【図1】は、防災グッズを所有している人の割合をグラフ化したものです。
時系列でみると少しずつではありますが、所有率が上がってきていることがわかります。2024年時点では7地区計で約30%の人が防災グッズを所有しています。
また2024年を地区別にみると最も高いのが東京50km圏、最も低いのが北部九州で、その差は14ptと大きな差がみられます。過去に震災を経験した仙台や南海トラフ地震のリスクが高い名古屋でも防災グッズ所有率は他の地区より高い傾向がみられました。
大きな被害をもたらした震災の翌年には近隣エリアで増加
気象庁の震度データベース検索(※1)によると、2010年以降の震度7以上の地震は5件で、2011年の東日本大震災、2016年の熊本地震で2件、2018年の北海道胆振東部地震、2024年の能登半島地震です。とくに熊本地震の発生地の近隣エリアである北部九州と、北海道胆振東部地震の発生地の近隣エリアである札幌に着目してみたいと思います。
※1:気象庁「震度データベース検索」より抜粋
https://www.data.jma.go.jp/svd/eqdb/data/shindo/index.html
【図2】は北部九州と札幌の防災グッズ所有割合を時系列でグラフ化したものです。
北部九州では熊本地震の翌年である2017年に所有率が前年と比べて3pt以上上昇、2021年長崎の豪雨の翌年も3pt以上上昇しています。札幌では北海道胆振東部地震の翌年の2019年に前年から10pt以上上昇しており、北海道胆振東部地震の際には、札幌を含む北海道全域で停電の被害が起きていたため、実際に被害に直面したことで防災グッズを備え始めた人も多いのかもしれません。
地震保険の加入率は10年間で若干上昇
ここまで防災グッズの所有割合をみてきましたが、地震保険の加入率をまとめたのが【図3】です。国土交通省による報告書(※2)によると、熊本地震では震度7が2回観測されるなど、過去に例を見ない大きな地震により、建築物に甚大な被害が発生しました。2000年以降に建てられた比較的新しい建物でも7棟の倒壊が発生しています。このような地震による建物や家財の損壊を補償してくれる地震保険ですが、加入率を7地区計の時系列でみると、3割程度を推移しており、若干ではありますが上昇傾向にあります。
※2:国土交通省「『熊本地震における建築物被害の原因分析を行う委員会』報告書のポイント」より抜粋
https://www.mlit.go.jp/common/001155087.pdf
有事の際の情報収集メディアにも変化
【図2】で確認したとおり、防災グッズの所有率は少しずつ上昇している傾向がみられましたが、防災グッズの定番である防災ラジオの所有率に絞ってみたのが【図4】です。防災ラジオとは、有事に災害情報を受信するためのラジオでAM/FM放送を受信できるだけでなく、災害時に必要な情報を流す特別なチャンネル(市町村の防災行政無線や緊急地震速報など)を自動で起動する重要な防災グッズの一つですが、10年間の所有率の推移はほぼ横ばいとなっています。
では、災害など有事の際にはどのように情報を収集しているのでしょうか。
【図5】は、「情報種類ごとの情報入手経路」で「事件・事故・災害」の際に地上波テレビ/ラジオ/新聞/ブログやSNSの書き込みと答えた人の割合を2015年と2024年で比較したものです。テレビやラジオ、新聞といったマスメディアで情報収集する人が減っている一方で、ブログやSNSの書き込みから情報収集する人が増加しています。
地上波テレビは減少傾向だが75.1%が有事の際の有効な情報源と認識
メディア別にみるとどのような傾向があるのでしょうか。【図6】は地上波テレビのスコアを年代別に確認したものです。
10年間で10pt程度低下しているものの、個人全体でも75.1%と高い水準を維持しています。特に男性50-60代、女性40-60代は8割を超えており、有事の際の有効な情報収集手段となっているのではないかと考えられます。
有事の際のSNS等での情報収集は若者だけにとどまらない
最後にブログやSNSの書き込みでの有事の際の情報収集割合についてもみてみました【図7】。
2024年には個人全体でみても16.1%と2015年と比較すると10pt増加しており、特に男女20-30代が20%以上と高くなっています。また男女50-60代でも1割程度が情報入手経路として利用しており、「速報性」の高いSNSが全年代に普及しつつある状況がみてとれます。その速報性は災害時にも大きく役立つ一方で、能登半島地震の際にはSNSでの虚偽情報が多くみられ、情報の正確性という点には気をつけて利用する必要があるでしょう。
有事の際には正確な情報収集が欠かせません。それぞれのメディアの強みや弱みを理解し適切な情報収集ができる備えも必要かもしれません。
時系列での意識変化を調べるには
いかがでしたか。
今回は防災意識にフォーカスを当て、10年間での変化についてまとめてみました。
「ACR/ex」では、20万項目にもおよぶ膨大なデータベースから生活者の時系列での年代意識変化を自由に調べることができます。
「ACR/ex」のサービス内容詳細は、以下より案内資料をダウンロードいただくか、毎週月曜13時~/金曜11時~に実施しているサービス定期説明会でデモ画面等を通して使い方を把握いただくことができます。
ご興味お持ちいただけましたら、お気軽に以下よりお申込みください。
【本記事で紹介したサービス】
・サービス名:ビデオリサーチ「ACR/ex」
・調査時期:2015年~2024年(4月~6月)
・対象地区:7地区(東京50㎞圏、関西、名古屋、北部九州、札幌、仙台、広島)
・ターゲット:男女12~69歳
・サンプル数:11,147s(2024年/7地区計) ※2015年~2023年は同程度