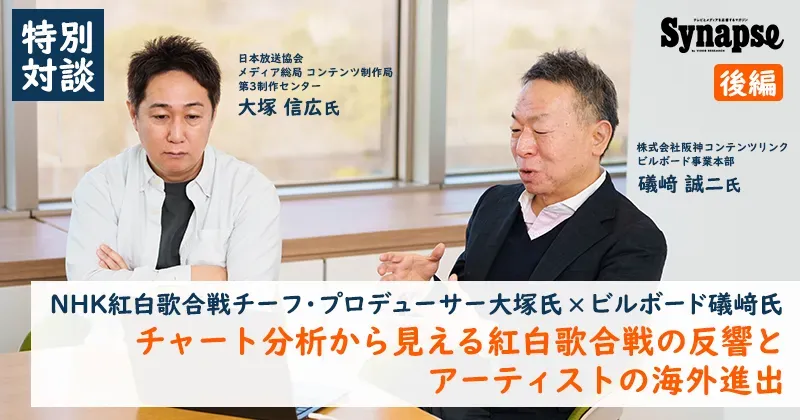【特別対談】NHK紅白歌合戦チーフ・プロデューサー大塚氏×ビルボード礒﨑氏(前編)|音楽番組とヒットチャートの関係性に迫る
<話し手>
写真左)日本放送協会 メディア総局 コンテンツ制作局 第3制作センター(エンターテインメント) チーフ・プロデューサー 大塚信広氏
写真右)株式会社阪神コンテンツリンク ビルボード事業本部 研究・開発部 上席部長 礒﨑誠二氏
近年、音楽業界においてストリーミングサービスの普及が進み、生活者の音楽視聴・購入行動が大きく変化しています。各放送局でも時代に合わせて改編を重ね、趣向を凝らした音楽番組を数多く生み出してきました。各コンテンツに特徴がみられるものの、その中でも長年国民に愛されているのが、2024年で放送75回を迎えた「NHK紅白歌合戦」です。
一方、音楽チャートも、時代とともに変化しています。生活者の行動変容に合わせ、複数のデータを合算したBillboard JAPANの音楽チャート「JAPAN HOT100」は、現在多くのメディアで使用されています。
今回のテーマは、「音楽番組と音楽チャートの関係性」です。「NHK紅白歌合戦」の制作統括を務めるNHKチーフ・プロデューサーの大塚信広氏と、Billboard JAPANを運営する阪神コンテンツリンク ビルボード事業本部 上席部長の礒﨑誠二氏に、話を伺いました。
「紅白歌合戦」制作のカギは"テーマ設定"
音楽番組はリスナーそれぞれが思う「ヒット曲」を決めるフィルターにもなる
まず、大塚さんに質問します。「紅白歌合戦」を制作するにあたり、チャートなど定量的なデータを活用されているのでしょうか?
大塚 音楽チャートに関しては、番組によって活用の比重が違ってくると思います。例えば私が担当している「Venue101」では、Billboard JAPANのヒットチャートをものすごく見ていますが、「紅白歌合戦」ではあくまで総合的に検討するための参考情報として捉えていますね。
「紅白歌合戦」でいえば、年ごとに決めているテーマや、番組内の企画・構成によって出演アーティストも変わってきます。「視聴者の皆さんは何が見たいのか」を軸に番組を制作しています。
礒﨑 年末に放送される各局の音楽特番は、それぞれの番組がどのような視点で1年間の音楽シーンを切り取ったのかが色濃く出ているようで、見ていて楽しいです。それぞれが違うし、Billboard JAPANの年間チャートとも一致していない。その差異こそが、番組の個性なのだと思います。
礒﨑さんは2024年の紅白を見て、1年間の音楽シーンがどのように反映されていたと感じましたか?
礒﨑 出演者の選出もさることながら、楽曲の順番や構成がとても精密に計算されている印象を受けました。1年間の総括を、番組トータルで表現しようという意思を非常に強く感じましたね。
大塚 その意識はありました。2024年は、元日に能登半島地震が発生しました。一方で、夏のパリオリンピックとパラリンピックでは多くのメダルを獲得。喜びと悲しみが入り混じった1年で、全員の気持ちを言い表すキーワードを1つに絞るのは難しいと思いました。
そこで、「そもそも音楽とは、誰に向けて届けるもの?」と、原点回帰の意味も含めて考え直してみました。その結果、「最も多くの人に聴かれた曲」だけを選ぶのではなく、「一人ひとりの心に響いている曲」を届けたいと思い、2024年は「あなたへの歌」というテーマを設定しました。

礒﨑さんの目から見て、「紅白歌合戦」などの音楽番組はどのように映っていますか?
礒﨑 音楽番組を観ると、作り手が楽曲や音楽に対してどう考えていらっしゃるかを感じることができて面白いですし、非常に勇気づけられます。というのも、Billboard JAPANのチャートを15年以上つくってきている身として、ヒットチャートの限界をひしひしと感じていました。
例えば、ここ10年ほどでストリーミングサービスが普及し、「何億回再生達成しました」という楽曲も登場しています。ですが、それだけでは一人ひとりがどんな状況でその曲を聴いているのかは分かりません。ストリーミングの再生回数の動きを意識して同じ曲をループしている人もいれば、会社帰り、電車の中で疲れを癒すためにじっくりと聴いている人もいる。CDセールスに関してもそうです。20万枚売れましたといっても、どういう人が購入したのか。中学生が一生懸命お小遣いをためて購入した1枚か、熱心なファンが100枚まとめて購入したものなのか。だから、単指標だけでヒット曲を決めるのではなく、複数のデータに基づいたヒットチャートは絶対に必要だと思い、Billboard JAPANのチャートを立ち上げました。
さらに言えば、「ヒットとはどういうものなのか」、「ヒット曲としてふさわしいのはどの曲か」は、それぞれリスナー自身が決めてほしいとも思っていて、それを抽出するのにヒットチャート以外のフィルターが必要だとも常に考えています。
ユーザーに音楽が届きやすくなった一方で
推し活が浸透してファンが能動的にチャートへ参加しようとする動きも
近年のストリーミング需要の増加に伴って、音楽シーン全体も変化はありますか?
大塚 ユーザーの音楽の楽しみ方は、どんどん変わってきています。デジタル技術の出現により、音楽そのものがユーザーの手に届きやすくなったのではないでしょうか。
それに伴い、再生回数1億回を突破した楽曲も続々と誕生しています。当初は「億超え!すごい!」と話題になっていましたが、今ではいわゆる「億のインフレ」が起きている状況です。
「シブヤノオト」(2016~2022年放送)などの音楽番組を担当していたときも、「よく見ると1億回再生がいっぱいあるぞ。これってすごいことなんだっけ?」と考えさせられたのを覚えています。
礒﨑 1億回突破した曲って今どのくらいあるんだろう...数えきれないくらい出てきて、あまりニュースにもならなくなりました。音楽チャートを提供する側としても、「億のインフレ」が起きている中、数字が独り歩きするのを抑えたいという思いはあります。最初は、1億回、2億回、3億回......と億単位で全部ニュースに上げていました。しかし、該当する楽曲があまりに多くなったので「1億回、3億回、5億回...と、奇数億回だけ取り上げれば良いのでは?」「1億回に何週で到達したという切り口のほうが、分かりやすいのでは?」など、基準を何度も調整しています。「すごいもの」を「すごい」とわかりやすく伝えるための調整ですね。
市場の変化に伴い、Billboard JAPANチャートでも指標の見直しをしていると聞きました。
礒﨑 ストリーミングが浸透していく中で、Billboard JAPANでは2022年12月からXのポスト数(当時はTwitterのツイート数)とルックアップ(インターネットに接続されている機器でCDを読み取りした回数)をチャートにおける指標から外しました。
理由は、「推し活」の過熱です。BTSの世界的な成功事例をきっかけに、いわゆるファンダム(熱心なファンの集団)の間で、自分の推しているアーティストをいかにヒットチャートに反映させるかという意識が浸透していったように思います。10年前、当時もいろいろな楽曲が流行っていたのですが、ニュースを出してもそこまで話題にならなかった。ところが今は、ファンの間で「Mrs. GREEN APPLEの『ライラック』がずっとチャートにいるよね」「King & Princeがそれを押さえて1位になったね」というチャートの動きが自然と話題になっている状況です。
その背景には、ファンの熱量が変わってきたのと、"ヒットチャート"というものが共通の話題としてあがってきたことが挙げられます。推しているグループとは別のグループのファンから「推しグループのチャートを上げるにはどうしたらいいか」の教えを乞うといった情報交換が頻繁に行われているのを見かけます。YouTubeで"歌ってみた"、"踊ってみた"に参加するのと同じように、ヒットチャートにも参加することでアーティストを推していこうという動きを感じます。
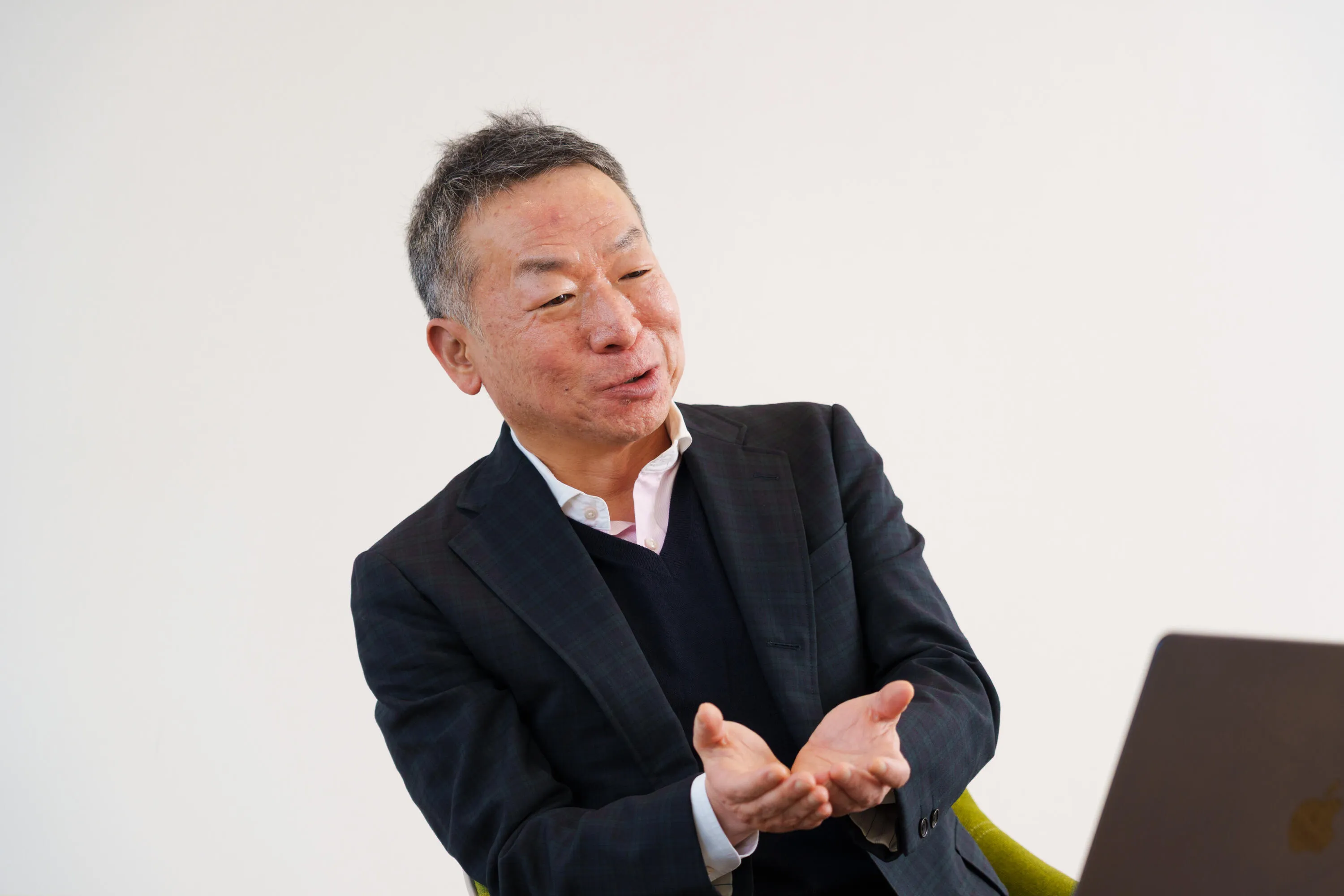
大塚 そうですね。昔はアーティストを推すときにはCDを買って、ライブに行って、グッズを買って......といういわゆる草の根活動がメインでした。しかしSNSが登場し、ストリーミングやYouTubeが浸透してきたことで、再生回数などの面で、アーティストに直接的に貢献できるようになった。ファンのアーティストとの向き合い方が変わってきましたよね。
生放送後にYouTubeで歌唱映像を配信!
メディアを横断した多様な指標で評価する時代に
「紅白歌合戦」も、放送後に各アーティストの歌唱映像をYouTubeの公式チャンネルで配信しましたよね。
大塚 歌番組とSNS、特にYouTubeやXは、親和性が高いですよね。もはやコンテンツを地上波だけで届けるのは、時代とあまり合っていない気はしています。もちろん、地上波で見ていただきたいという気持ちは強く持っていますが、NHKプラスでもコンテンツを提供しているので、番組紹介の一環でXやLINEも活用しています。
今回も、YouTubeで一部ではありますがコンテンツを配信することで、見ていなかった人に対し「紅白ってこんなシーンがあったんだ」という気づきを提供できる機会になったのかと思います。
礒﨑 今回は、YouTubeに上がるタイミングが早かったですよね。そして、そこからバズっていくのもとても早かった。
大塚 そうですね。2022年からNHK MUSICの公式YouTubeチャンネルに動画を上げているのですが、2024年はB'zの『ultra soul』、米津玄師さんの『さよーならまたいつか!』、藤井風さんの『満ちてゆく』、こっちのけんとさん『はいよろこんで』などが話題になりました。
礒﨑 番組の話題って、SNS上でどのくらい持っている感覚ですか?体感で。
大塚 「紅白歌合戦」は、1週間から10日ですかね...。他の歌番組は、3日くらいの感覚です。
礒﨑 ああ、同じです。私たちのチャートがニュースで話題になるのも、もって3日くらいなんです。
大塚 そうですか!3日ってすごく短いですよね。今後はもっと早くなっていくかもしれない。個人的にはコンテンツって"ストック型"と"フロー型"の2パターンあると思っていて、ストック型になろうと意識して作った時は、少し長めに届く感覚がありますね。
礒﨑 通常、番組ってデータを参考にしながらキャスティング、構成を考えていくと思うんですけど、それで作られた番組が最後に他のメディアで視聴率としてデータで語られるじゃないですか。それについてどう感じてらっしゃいますか?
大塚 難しい問題ですね。個人としてはエンターテインメントに携わる人間として皆さんに見ていただきたいという想いで番組を作っているので、視聴率が良かったら嬉しいという気持ちはもちろんあります。
一方で、さまざまな指標で評価する時代になってほしいなとも思っています。多分、番組制作に携わるディレクターやプロデューサーの大半は同じことを思っていると思うんですけど、みんな自分が作った番組に誇りを持っているんですよね。それが多くの人に届けられたかを知る方法として、例えば視聴率のほかにも、NHKプラスでは平均の2倍の再生回数を取って、YouTubeも平均より3倍も再生されて...と、総合的に見て「とても良い見られ方をしている番組だ」と捉えてもらえるようになるといいですよね。
※続く後編では、チャート分析から見える紅白歌合戦の反響と、アーティストの海外進出について伺います。