放送メディアの変化と不変的な価値とは?【VR FORUM 2025】
[登壇者](右から)
日本テレビホールディングス株式会社
日本テレビ放送網株式会社
代表取締役社長執行役員 福田 博之 氏
株式会社テレビ東京ホールディングス
株式会社テレビ東京
代表取締役社長 吉次 弘志 氏
株式会社ビデオリサーチ メディアデザイン研究所 所長 奥 律哉
視聴行動や広告市場の構造変化が進む中で放送局はどのように進化し、社会的使命をどう維持していくのか。日本テレビとテレビ東京のトップを迎え、コンテンツ戦略やビジネスモデル変革、放送メディアの「不変的価値」について、ビデオリサーチ メディアデザイン研究所の奥が話を聞きました。
テレビを取り巻く環境変化に対応する、日本テレビ・テレビ東京のビジネス戦略
セッションの冒頭では、電通が発表した「2024年 日本の広告費」と、動画配信プラットフォームの利用実態を把握した、ビデオリサーチのサービス「STREAMO(ストリーモ)」のデータから見える自宅内のTVデバイスにおける動画視聴実態のポイントを奥が説明しました。
・日本の総広告費は、前年比104.9%となる7兆6730億円
・インターネット広告費は伸長を続け、総広告費の47.6%を占める
・テレビメディア広告費(地上波+衛星メディア関連)は、近年、伸びが横ばいで、シェアは21.9%
・テレビメディアデジタル広告費は654億円で、前年比146.3%の伸びを示し、今後も成長が見込まれる
・自宅内のTVデバイスにおける利用分数シェアは、C層、T層、M1層、F1層、F2層など、若年層を中心にコネクテッドTVの視聴が2割前後を占める
視聴環境が変化する中で、テレビ局はどのような経営戦略を描いているのか、両氏に尋ねました。
まず、福田氏が日本テレビの経営戦略を説明。幅広い年代での個人視聴率を獲得しつつ、13~49歳男女をコアターゲットと設定し両面で視聴率をしっかり取っていくことに加え、前年実績を必ず超えることを目指していると伝えました。
同氏によると、日本テレビの編成戦略で大切にしていることは、「日常と祝祭」だといいます。「日常」とはレギュラー番組で、「祝祭」は単発の大型コンテンツ。後者は、多くの人が感動を共有できるコンテンツで、『24時間テレビ』や『箱根駅伝』が代表的ですが、2025年には、漫才&コント大会『ダブルインパクト』や、『THEグルメDAY』といった新たなコンテンツも加わりました。
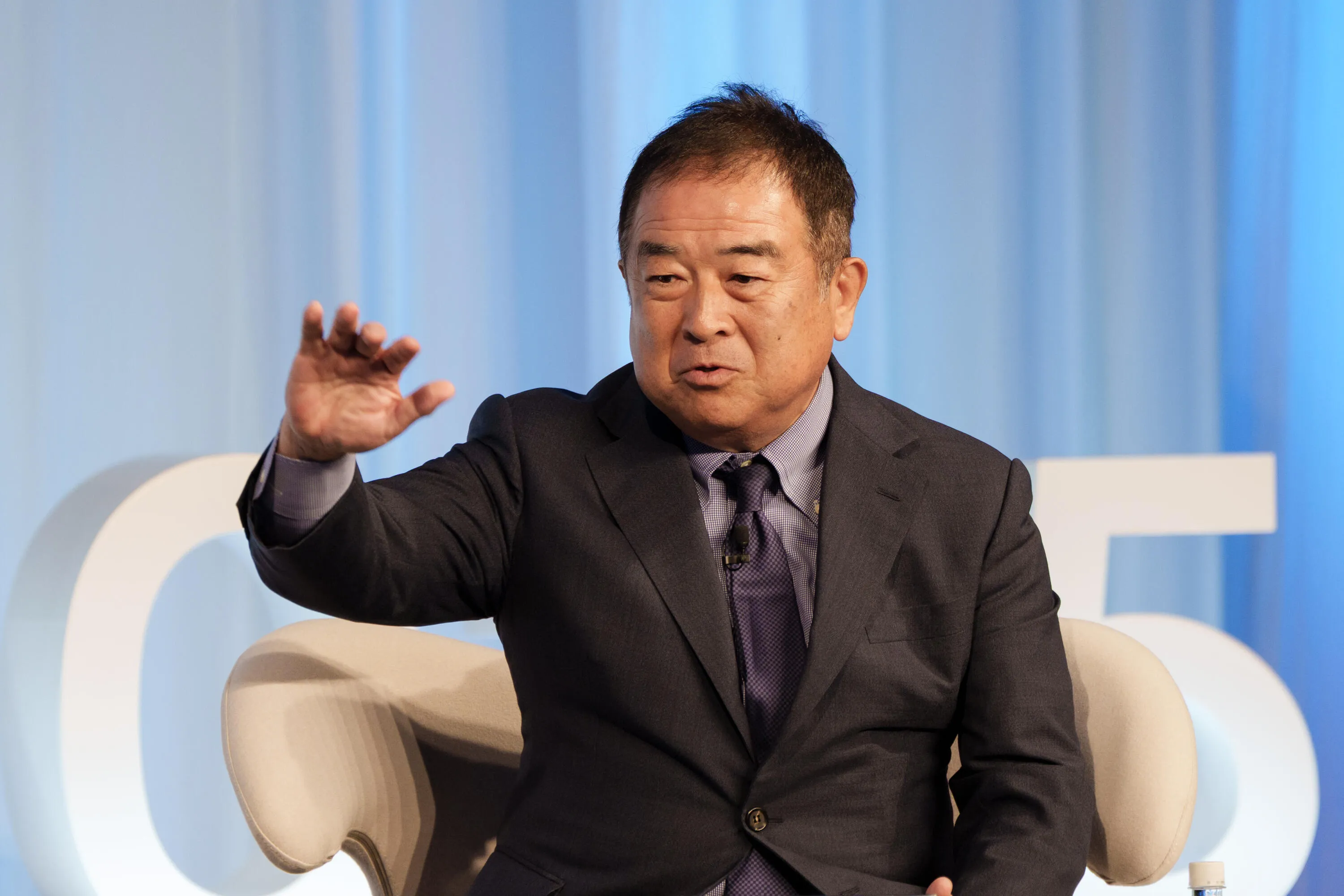
編成戦略について、福田氏はさらに、「地上波は『思いがけないものに出会える』『ターゲットの外側にも当てられる』という、デジタルメディアとは異なる強みがあるので、セレンディピティを大事にしてコンテンツ作りを行い、広告価値も生み出そうとしている」と述べました。
続いて、吉次氏がテレビ東京の経営戦略を説明。テレビ東京は、経済を中心とした報道番組に加え、他局にはない独自色の強いバラエティとドラマ、さらにアニメを強みとしており、今後も継続して注力していく方針を示しました。
さらに、乳幼児向け番組『シナぷしゅ』を紹介。企画段階では、「ターゲットが少ないため視聴率が見込めない」との懸念があったものの、いざ始めてみると番組を軸にさまざまな事業展開の可能性を見出し、今ではこのような取り組みにも積極的に力を入れていきたいと語りました。
また、長年にわたり放送されているドラマ『孤独のグルメ』やバラエティ『Youは何しに日本へ?』といった番組は、「テレビ東京らしい独自性を評価され、ファンの存在が番組を超えた多様な展開を可能にしており、それがテレビ東京の強みである」と述べました。
人がやらないことをやり、まだ見ぬ「おもしろい」を世界に発信する
現在、コンテンツ、IPが中心と言われ、国を挙げて日本のコンテンツを海外に展開していこうという流れがあります。日本発のコンテンツの海外売上高は、鉄鋼や半導体産業を上回る規模になっており、コンテンツを作る放送事業者は今後も貴重な役割を果たすことが期待されます。官民連携もしくはネットで広くコンテンツを発信していく時代を踏まえて、海外展開の戦略について両氏に伺いました。
吉次氏は、「テレ東VISION2035」を紹介。「人がやらないことをやり、まだ見ぬ『おもしろい』を世界に発信すること」を、会社の柱にしたいと述べました。また、コンテンツIPを核としてさまざまな領域に展開するビジョンであるCaaS (カーズ:Contents As A Service)について説明。コンテンツを放送するだけでなく、マーチャンダイズ、イベント、配信などに展開して、コンテンツごとに経済圏を作ることを進め、放送以外の分野をどんどん広げていく必要性を語りました。
放送だけに頼らない収益構造改革として、テレビ東京の売りの一つである「アニメ」についても言及。テレビ東京は、早くからアニメ局を設け、アニメの権利を多面的に展開するノウハウを蓄積してきたといいます。

テレビ東京は、放送と配信のセグメントを分けて収益の管理をしていますが、2023年度は、「放送以外の営業利益」が、放送を上回りました。その背景として、『NARUTO-ナルト-』や『BLEACH』が代表するコンテンツの強さは前提として、商品化やゲーム化などアニメビジネスのグローバル成長も大きく、アニメの売上高は、2022年度に200億円を超え、2025年度は240億円に達しています。地域別のシェアでは、中国が34%、北米が29%となっており、今後は、アジア、中東、ヨーロッパへの展開も強化していきたいとの考えです。
また、新たなコンテンツ開発として始めた「恐怖心展」などの展覧会イベントも人気を集めていると言います。
吉次氏の話を受けて奥は、「テレビ局はこれまで放送ファーストでタイムとスポットの収入が柱だったが、これからコンテンツとIPを中心に取り組んでいくにあたり、社内の制度や社員の意識改革は進んでいるのか」と尋ねました。
吉次氏からは、「放送収入のウェイトはまだ高いものの、タイムとスポットの収入だけでは成り立たないことは十分に認識している」との回答。アニメに限らず実写作品でも、これまでの一般的な"地上波での放送後に配信する"パターンだけでなく、先に配信プラットフォームに出してから放送する"配信ファースト"など、いろいろなパターンが増えてきているといいます。社員の意識もこの10年でかなり変化し、多様なパターンへの対応も念頭においたビジネス展開も考えられるようになったとのことで、今後もこの流れを強化していきたいと述べました。
「日テレ、開国!」をスローガンに、グローバル展開を積極的に進める
福田氏は、2025年5月に発表した中期経営計画のスローガン「日テレ、開国! Gear up, go global」について説明。自社のコンテンツを地上波やオウンドのプラットフォームだけにとどめず、グローバルの接点を探りながら、外資のプラットフォームにも展開する方針であると述べました。
日本テレビは、日本でかつて放送されたリアリティーショーをイギリス版にした『¥マネーの虎』をグローバルで54バージョン展開して評価されています。最近では、ドラマ『ホットスポット』、『はじめてのおつかい』フォーマットを、Netflixで全世界配信しており、「これまで日本で放送したコンテンツが信じられないくらいのスピードで世界に広がっていることを実感している」と語りました。
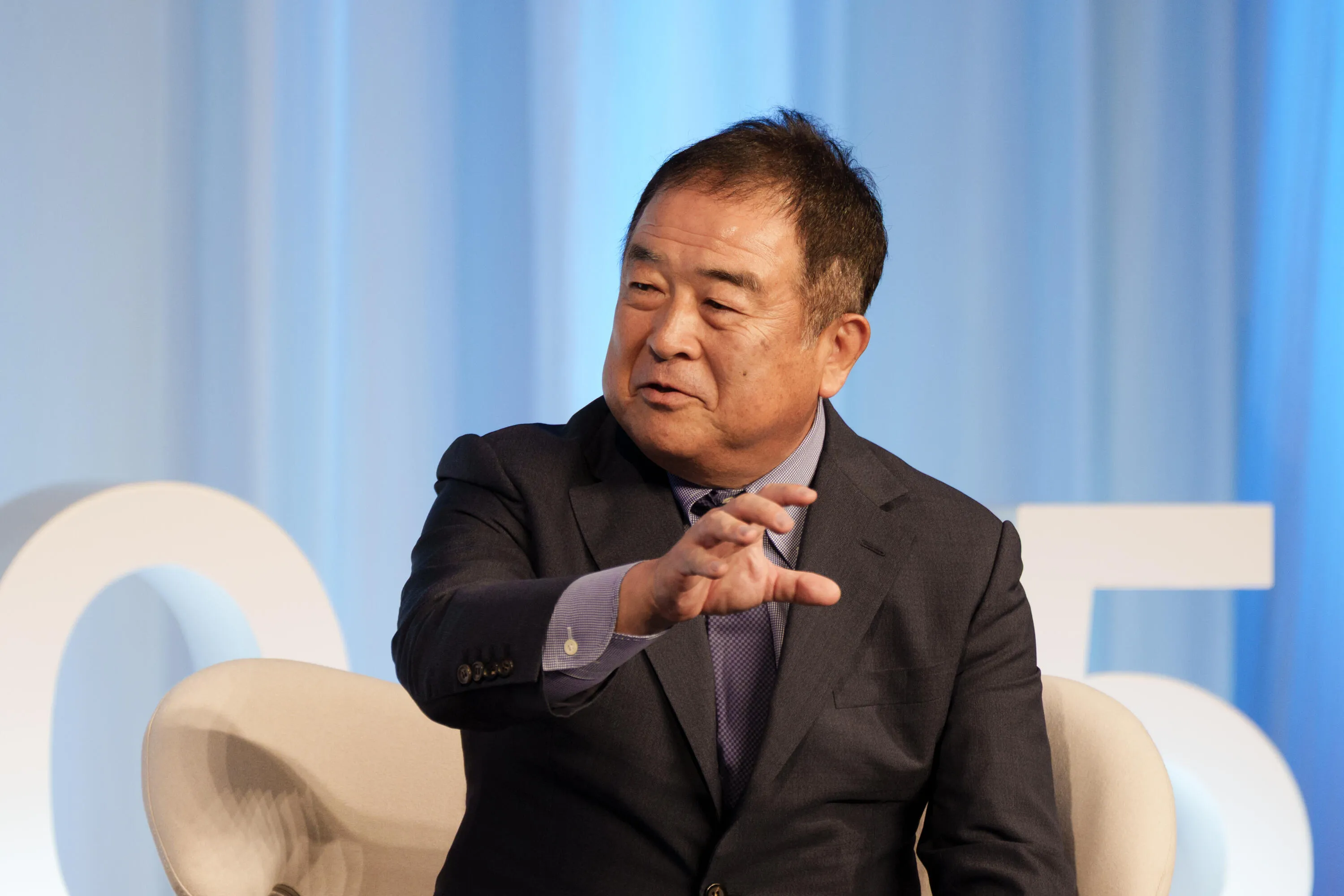
奥は、コンテンツのグローバル展開について、配信プラットフォームにおけるコンテンツへの広告の出し方とそのマネジメントが課題だと言います。「オウンドメディアと違い、コンテンツだけを出してしまうと広告セールスが不透明になったり、コンテンツのどこのタイミングでどのような広告が入るか分かりにくくなる」と懸念を挙げました。
これに対し福田氏は、「自分たちが提供しているコンテンツに広告が後から設定されて、広告が自分たちでコントロールできないと、ブランド棄損や収益面のリスクがあるので、避けたい」としたうえで、「(プラットフォーム側から)視聴データをフィードバックいただき、そのデータの利活用をも許していただけるなら共同セールスのような別の取り組みも考えられる」と見解を伝えました。
これを受けて奥からは、配信プラットフォームでの視聴データとして、ビデオリサーチが提供しているデータサービス「SoDA(ソーダ)」を紹介。「データ上でも、日本のコンテンツは海外でわれわれの想像以上に視聴されていることが確認できている」ことも合わせて伝えました。
さらにコンテンツとは別のIPのグローバル展開も考えていると言います。古立善之氏や前川瞳美氏など、日本テレビの人気番組を手掛ける多彩なクリエイターたちの能力や創作活動そのものをIPとし、それを軸にビジネスを展開する、"クリエイターIP"のグローバル展開です。グローバルでの実績や評価も少しずつ積んできていると述べたうえで、さらなる体制強化として2025年に立ち上げた、海外向けバラエティ番組制作スタジオ「GYOKURO STUDIO」を紹介しました。ここでは映像に限らず、デジタルクリエイティブを研究して、世界に支持されるコンテンツ作りを始めていると述べました。
AIやバーチャル技術で進化する、テレビの現場
番組のコンテンツ制作で、AIやバーチャルスタジオなど新しいテクノロジーを活用する場面も増えてきています。
このことについて福田氏は、AIエージェントを、権利処理の代行など制作関連部門の業務に活用することで、業務効率を上げ年間約10万時間を生み出そうとしていると発言。さらに、「クリエイターの創造力」と「AIによるヒットの再現性能力」を掛け合わせる実験を繰り返し行っており、そこからこれまで見たことのないヒットコンテンツが生まれてくることを期待していると述べました。本セッションのためにAIの活用事例として、AIにより制作された福田氏が出演する動画の上映も行われ、会場は盛り上がりました。
吉次氏は、テレビ東京は報道スタジオを中心にバーチャルプロダクションスタジオを導入していると言います。例えば、『ワールドビジネスサテライト』(以下、WBS)では、背景がすべてバーチャルになっており、映像表現の高度化が図れるのをはじめ、スタジオの建て込みや壊しが一切ないことから運用の効率化、その分の収益への貢献が見込めることをメリットとして挙げ、「テレビ東京は、経済関係のニュースが多く、グラフの作成などにバーチャルはかなり力を発揮している」と述べました。
地上波放送の社会的役割と不変的な価値とは
近年、選挙報道や選挙活動においてSNSが活用されることが多くなったことに伴い、フェイクニュースやフィルターバブルが大きな問題になっています。 広告主目線では、アドフラウドやブランドセーフティーなど、情報空間の健全性が問われており、総務省によりデジタル広告のガイドラインも作られました。「情報の信頼性」がどこにあるかが不透明になっていると奥は語ります。
ビデオリサーチのマーケティングデータ「ACR/ex(エーシーアール エクス)」を見ると、情報の信頼性について、テレビは他のメディアより高いものの、2015年が39.2%だったのに対し、2025年は31.2%と下落。対して、企業・ブランドのサイトは10.6%から14.0%、ブログやSNSの書き込みは2.7%から4.0%と上昇しています。
テレビの信頼性について2社の課題意識や取り組みを聞きました。

福田氏は、テレビの信頼性が落ちていることを懸念していると吐露します。日本テレビは、テレビの強みである信頼性をアピールするため、2025年の東京都議会議員選挙と参議院選挙、総裁選のタイミングで、選挙報道プロジェクト「投票前に考える それって本当?」を実施。フィルターバブルなどが問題視される時代に、"本当"は何かということをしっかり伝えていこうとしました。
例えば、SNS上で外国人の生活保護受給世帯や受給割合が話題になっていましたが、本当の数字を調べると、SNS上で話題になっていることが事実でない場合も多いことが判明。そのことを、地上波とSNSで伝えました。
同氏は「このキャンペーンは感情的にならず、しっかりと事実を見定める必要性を伝えている。選挙の時に限らず、災害時や社会的に影響の大きな事件が起こったときもこのキャンペーンを行っていきたい」と、この取り組みの意義を語りました。
吉次氏は、テレビ東京は、大株主である日本経済新聞社との連携が重要な課題であると述べました。日本経済新聞や関連の出版物はリテラシーが非常に高い層を読者として獲得しているのが特徴です。テレビ東京は、新聞や雑誌よりも柔らかいタッチで経済情報にアプローチをして、視聴者に届ける作りになっているとのこと。
『WBS』『Newsモーニングサテライト』などのニュース、『ガイアの夜明け』『カンブリア宮殿』などのドキュメンタリー、最近力を入れているという動画配信サービス「テレ東BIZ」オリジナルの池上彰氏のインタビューシリーズや悩める大人の相談ものなど、豊富なコンテンツを例に挙げながら、「日本経済新聞グループの中で、テレビ東京はユーザーの裾野を広げる役割を担っている。そのための手段として、地上波、BS、配信に力を入れ、"経済"を前面に信頼ある情報源を提供している」と自社の役割を説明します。

各局の情報の信頼性のための取り組みを受けて、奥は「ファクトチェック、ジャーナリズム、公正中立性などを謳いながら、これらをすべて実現しようとすると、視聴率やクライアントセールスの問題もあり、民放では難しさも多い」と見解を述べました。
これに対して吉次氏は、「何を重視するか」を割り切ることが必要だと言います。例えば、情報番組『Newsモーニングサテライト』などは、「マーケットに強く関心がある層だけでなく、経済全体を見るとき、マーケット情報が役に立つことが理解いただける方に見ていただけるとうれしい」と伝えました。
続いて奥は、「スポーツ」を話題に。2026年のWBCにおいてNetflixが日本国内向けに独占配信を行うことを例に、「スポーツ中継は、これまで地上波が育ててきた代表的コンテンツであり、誰でも無料で見られることに価値があった」と述べました。
福田氏は、WBCなどのスポーツは、国民の圧倒的な関心事でもあるので、自局はもちろん他局であっても「テレビでやりたい」という思いが強くあると返答。「テレビは圧倒的なリーチメディアで、リーチすることで大きなムーブメントを起こす力を持っている。2025年の箱根駅伝は全国で5540万人、世界陸上は約8000万人にコンテンツが届いている。テレビ局にはこれほどのムーブメントを起こす力があるし、ノウハウも持っている。それを実現させるために、自分たちが今、何をできるのかを次に考えていきたい」と放送局ならではの力と想いに言及しました。
日本テレビとテレビ東京の「Next STANDARD」
最後に、今回のフォーラムのテーマ「Next STANDARD」について、両局の今後の展望を伺いました。
吉次氏は、「まだ見ぬおもしろいを共に作る」ことを社内の共通キーワードに掲げて取り組むことを強調。「テレビ東京は、他の在京キー局にリーチや物量面で勝負を挑んでもかなわない。ニッチな領域で独自性を発揮して面白いことを考えることを徹底的に追求していきたい」と述べました。
福田氏は、「コンテンツの力で、"世界"を変える」というメッセージを提示。コンテンツの力を信じ、現状や常識を変えるほどに、テレビで熱狂を生んでいきたいと熱く宣言しました。また、テレビ広告を進化させる、アドプラットフォーム開発プロジェクト「Ad Reach Max(アドリーチマックス)」をTBSテレビと連携し進めることにも言及。同プロジェクトは現在トライアルを重ね、問題なく、ポジティブな評価も届いているそうです。今後は全国の放送局にも参加いただきたいと述べ、セッションを締めました。

全19セッション分のレポート公開中!こちらから




